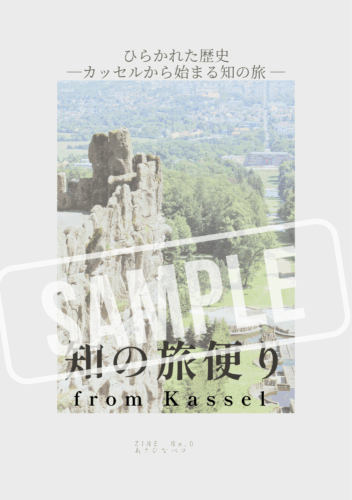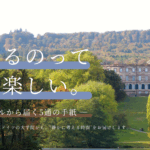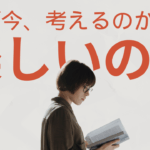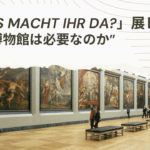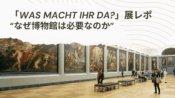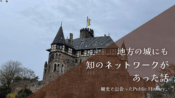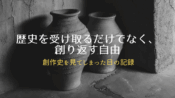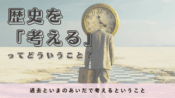Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているWebライターのあさひなペコです🐣
私は夕食の場でたまたまカッセル大学のWebサイトを見た時に、ドイツで歴史と公共という学問を見つけました。
最初は
歴史好きだし、Webライターの経験を活かせる!!
くらいのライトな気持ちだったんです。
そんな私が、公共史(Public History)と出会って、見える世界が変わっていきました。
今回は 「なぜ今、“公共史”が面白いのか」をテーマに、皆さんに公共史って楽しいんだよ!をご紹介したいと思います。
公共史という学びとの出会い
私は2024年の夏に入学しています。
その時は学問として「公共史」を学ぶことはなく、妊娠中ということもあり、可能な範囲で授業に参加し、ドイツでの学生生活を体験していました。
可能な範囲での参加、そして無期限での期末レポートを提出という感じで、そのまま7月に息子爆誕。
そして2024/25年の冬学期。
ついに受講することとなった「Einführungsmodul Master Geschichte und Öffentlichkeit(修士課程 歴史と公共 入門ゼミナール)」。
この入門ゼミを受けるまで、方法論もろくに知らず、正直
「パブリックな歴史ってどういうこと?」
と首をかしげてました。
ゼミが始まり、文献を読んだり参加者同士で話していったりしていくうちに、
「歴史を研究するだけじゃなく、社会とどうつながるか」
を考える分野だと知って、ぐっと心が動きました。
それまで学んできた「歴史」は、過去の出来事を追うもので、社会と直接つながる場面はあまりなかった。
でも「公共史」は、むしろ人と人のあいだに「歴史が生きている」感覚を教えてくれました。
ドイツでこの言葉に出会ってから、私は「公共史ってなんだろう?」という問いを持ち歩くようになっていきます。
それは「新しい学問」を超えて、「知る」と「生きる」をつなぐためのまなざしのように感じられました。
公共史とは「社会の中で生きる歴史」
公共史を簡単に言えば、歴史を社会と共有する学びです。
研究室の外で、どのように過去が語られ、受け取られ、記憶されていくのかを考える。
でも私が実感したのは、定義よりも空気のようなものでした。
展示や街の記念碑、ニュースの語り方。
そのどれにも「語る人」がいるという事実があるのです。
博物館と街の中で感じたこと
たとえば、博物館で展示の説明文を読むとき。
そこに書かれている言葉の選び方ひとつで、「この過去をどう見てほしいか」が伝わってきます。
また、街を歩いていて偶然出会う記念碑やプレート。
それを「誰がどんな思いで置いたのか」を想像すると、その瞬間にも、ひとつの公共史が立ち上がるんです。
そんな見方の変化もあり、私にとって公共史は、学問というより“まなざし”に近いものとなっています。
歴史の語り方に目を向けること。
そこにある意図や感情を受け取ること。
それがこの分野の面白さであり、いまの社会を考えるヒントにもなっていると感じています。
「なぜ今」公共史が面白いのか
公共史という言葉を知ってから、私はずっと考えています。
なぜ、この時代にこの分野が生まれ、広がっているのだろう?
その答えは、私たちが「語り」とどう向き合うかにある気がしています。
語りがあふれる時代に
いま、誰もがSNSで歴史を語り、AIが記録を要約し、ニュースやドラマが過去を再解釈していく。
語りがあふれる社会では、
「何を事実とし、どんな言葉で語るのか」
という選択が、これまで以上に大切になっているように感じます。
公共史の面白さは、過去を扱いながら、その裏にある語り手の存在を意識させてくれるところにある。
歴史を語ることは、過去を整理するだけでなく、「いまを生きる私たち」の姿を映し出す行為でもあるのでしょう。
過去を語ることは未来を考えること
過去を語るというのは、「どんな世界を未来に残したいか」を考えることでもあります。
語りの形が変わり続ける今だからこそ、公共史のまなざしが問われているように感じます。
記憶をどう残すか、
誰が語るか、
何を語らないか。
そうした選択の一つひとつに、社会の多様な声が反映されていく。
私はそこに、学問を越えた希望のようなものを感じています。
学びと日常をつなぐ「共有」という試み
授業で公共史を学ぶことと、日常の中でその感覚を見つけること。
その両方を行き来する時間が、私にとっての「学び」になっています。
ここでは、公共史が日常のどんな場面に潜んでいるのかを、考えてみたいと思います。
小さな展示と個人的な記憶
たとえば、地域の小さな博物館や学校の展示。
そこには専門家ではない人たちが語る“身近な歴史”があります。
その声に耳を澄ませると、「歴史は誰のものなのか」という問いが、ふと浮かび上がるようです。
学問というより「対話」のかたち
公共史を学んでから、私は「過去を語る」ということが「昔を懐かしむ」ことではなくなりました。
むしろ、「いまを生きる人たちと対話する」ことに近いのではないでしょうか。
学問と日常のあいだにある「共有」のかたち。
そこに、公共史の本当の面白さがあると感じています。
ZINEと講義、そして「語ること」のこれから
大学での研究や授業、そしてZINEづくり。
それらを通して、私は「語ること」の可能性、そして限界を探しています。
学問が社会に開かれるとき、何が起こるのか──
その実験を、いままさに続けているところです。
デジタルZINEという実験の場
私にとってデジタルZINE『知の旅便り』は、同人誌というだけではなく、学問と日常をつなぐ実験の場です。
授業で学んだ理論や、街で見た展示、誰かとの会話で生まれた小さな問い。
それらを「論文」でも「日記」でもないかたちで言葉にしてみる。
その試みの中で、「語ること」の新しいかたちを探しています。
たとえば、0号では「考える」ことや「公共史」をめぐって、「学ぶってどういうこと?」をテーマにまとめました。
メールマガジン『知の旅便り from Kassel』の登録特典として、無料で読める小冊子になっているので、最初の1冊としてちょっと覗いてみてもらえたら嬉しいです📬
語りの橋をつくるということ
公共史を学ぶというのは、過去といまをつなぐ「橋」のつくり方を学ぶことでもあるように感じています。
そしてその橋は、研究者だけのものではなく、誰もが渡れる小さな橋であってほしい。
だから私は授業や育児の合間、時間の許す限り「語ること」と「聞くこと」のあいだを行き来しています。
【おわりに】「語る」という行為を、もう一度信じてみる
もしかしたら、公共史の面白さって、「語る」という行為をもう一度信じてみることなのかもしれません。
誰かの言葉に耳を傾け、自分の言葉を少しずつ磨いて、過去と未来のあいだに橋をかけていく。
このブログでは、そんな「歴史を語る」試みを、少しずつ言葉にしています。
もし興味があれば、ZINE『知の旅便り』の0号(無料版)ものぞいてみてください。
以下より詳細が確認できます👇
そこではもう少しゆっくりと、「公共史」というまなざしをめぐる旅を続けています。