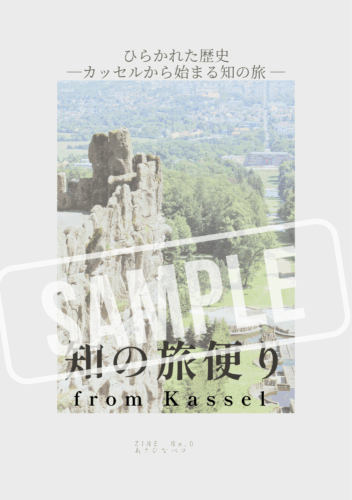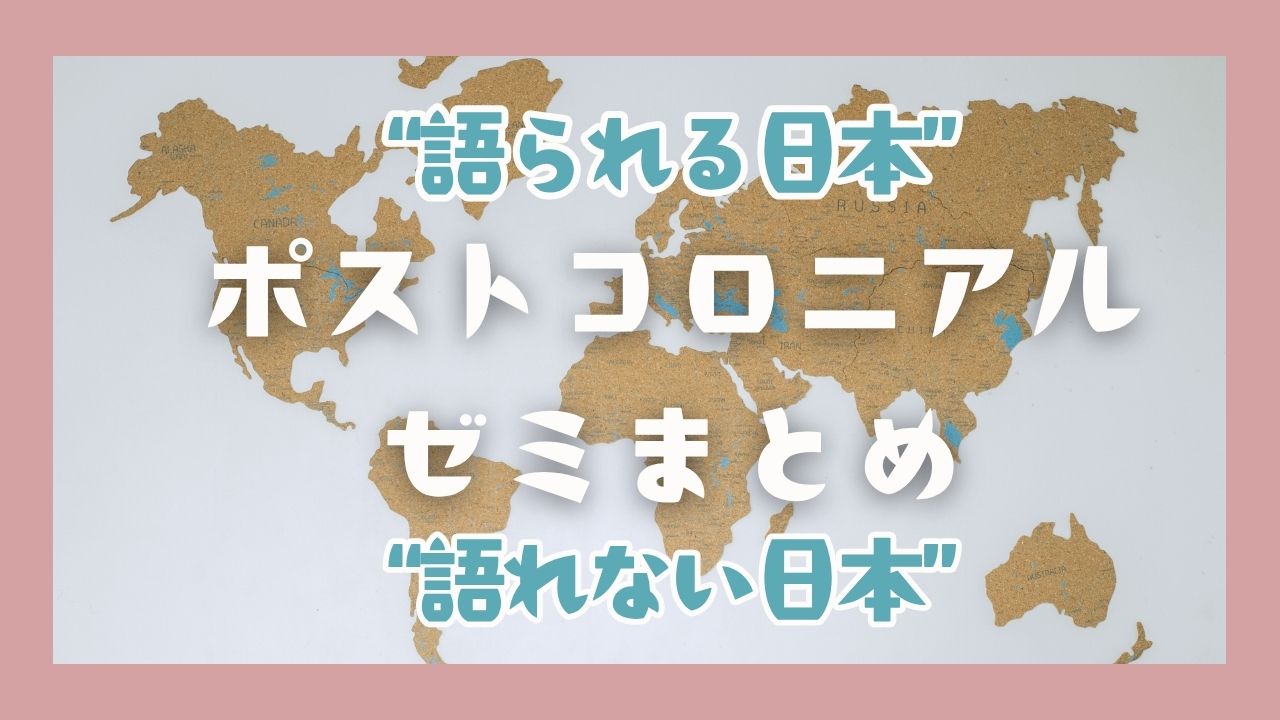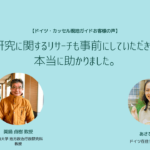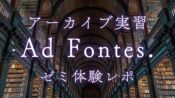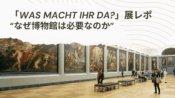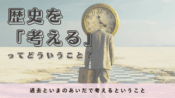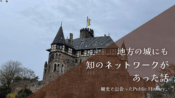【ポストコロニアルゼミ】“語られる日本”と“語れない日本”。カッセル大学の夏学期で考えたこと
\ この記事を共有 /
【ポストコロニアルゼミ】“語られる日本”と“語れない日本”。カッセル大学...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです
今回は、カッセル大学の修士課程「Geschichte und Öffentlichkeit(歴史と公共性)」で開講された2025年の夏学期ゼミ
「Postkolonialismus: Ziele, Grenzen und kontroverse Debatten」
に参加したときの体験をまとめます。
「ポストコロニアル?なんか難しそう…」と思った方も大丈夫!
実際の授業はかなり“生きた議論”で、理論だけじゃなく日常にも直結する内容でした!
ぜひ最後まで読んでみてね🌏✨
【参加きっかけ】先生が日本にめっちゃ詳しかった件
実はこのゼミを取った理由、ちょっと個人的なんです。
担当のBüschel先生が、以前別の授業で——
なんと!日本の歴史研究者・眞鍋貞樹さん(元拓殖大教授)の研究テーマだったカール・ルードルフに興味を示していて。
しかも眞鍋先生の研究資料、私が一式引き継いでいたんです😳
「これは…話しかけるチャンスでは?」と思い、先生との関係づくりも兼ねて受講を決意(笑)
あと単純に、先生が日本の話をするときの熱量がすごい。
発表前も「日本の明治時代の文明開化をちょっと説明しますね」と学生に語り出してて、「あ、絶対この人、日本に興味あるわ…」って確信しました。笑
【授業の様子】“ポスコロ理論”の核心に迫る夏
ゼミの正式タイトルは
「Postkolonialismus: Ziele, Grenzen und kontroverse Debatten(ポストコロニアル理論:目的・限界・論争)」
使用テキストは超王道。
サイード『オリエンタリズム』、
楽天ブックス
¥1,708 (2026/02/25 21:51時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
楽天ブックス
¥1,708 (2025/10/09 21:11時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
ホール「The West and the Rest」、
楽天Kobo電子書籍ストア
¥1,867 (2026/02/25 21:51時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』
楽天ブックス
¥2,970 (2026/02/25 21:51時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
などなど、ポスコロ理論の重鎮。
聞いただけで“理論の森”に迷いそうだけど(笑)授業では、先生がその都度、時事問題や学生の国の例を挟みながら進めてくれて、かなり対話的でした。
たとえばサイードの話をしているときに、「ところで日本はどこに位置すると思いますか?」とふられた瞬間、教室の空気がちょっと止まる。
そう、東アジアはポストコロニアル理論の“盲点”なんです。
【プレゼン】「日本は“語られる”けど、“語っていない”」
私の発表テーマはこれ👇
「Warum bleibt Japan trotz seiner kulturellen Sichtbarkeit in der postkolonialen Theorie so unsichtbar?」
(日本はなぜ文化的には見えているのに、理論の中では“見えない”のか?)
サイードが分析した「オリエント」は中東が中心で、日本や中国、韓国は脇役。
ホールの「The West and the Rest」では、“アジア”がまるっと一括り。
発表のとき、先生がにやっとして言った。
「Ah, Sie sprechen über die blinden Flecken(盲点ですね)」
そう、その“盲点”こそ私が話したかったこと。
ドイツで「Chinese?」と聞かれて「Ich bin Japanerin」と答えると、「Ah, Fujiyama! Sushi!」と返ってくるあの瞬間——まさに他者化(Othering)の現場なんです(笑)
善意なんだけど、ちょっとズレてる。
「私」が「イメージの日本」に置き換えられてしまう感じ。
【理論との出会い】“Asia as Method”という希望
スピヴァクが言うように、
“The subaltern cannot speak.”
——語られてはいるけれど、語ってはいない。
それをどう乗り越えられるか考えていたときに出会ったのが、台湾の理論家の陳光興(クアンシン・チェン/Kuan-Hsing Chen)の『Asia as Method(方法としてのアジア)』でした。
彼は「アジアを語る」のではなく、「アジアから語る」ことを提案している。
つまり、西洋理論の“外側”に立って、アジア内部の経験や記憶から理論を再構築する視点。
先生もこの部分では「Das ist spannend!(面白いね!)」とテンション上がってました😄
【授業後の気づき】“語る”って、対話なんだ
授業の終わりに先生が言った言葉が印象的でした。
「今日のテーマに“答え”はありません。でも、どんな“問い”を持ち帰るかが大事です。」
以来、私はノートの最後に“今日の問い”を一つだけ書くようにしています。
たとえば……
「私たちは誰の理論で語っているのか?」
「そして、誰の声がまだ聞こえていないのか?」
ZINEにつながる話
この経験をもとに、ZINE『ひらかれた歴史 ─ カッセルからはじまる知の旅 ─』を制作しました。
今後は、“語られる日本と語れない日本”をテーマに、“アジアから語る”という方法についてもさらに探っていく予定です📖
最後に
ポストコロニアル理論って難しそうに見えるけど、突き詰めると「誰が語るか」より「どう語るか」。
そして、その“対話の余白”こそが大事なんじゃないかなと思っています。
その一歩を探すことこそ、ポストコロニアルな対話の始まりかもしれません。
最後まで読んでくれてありがとダンケ🌿
あさひなペコ