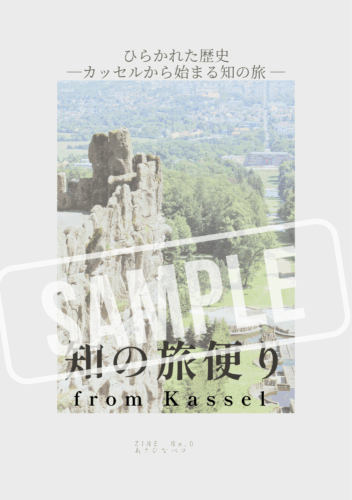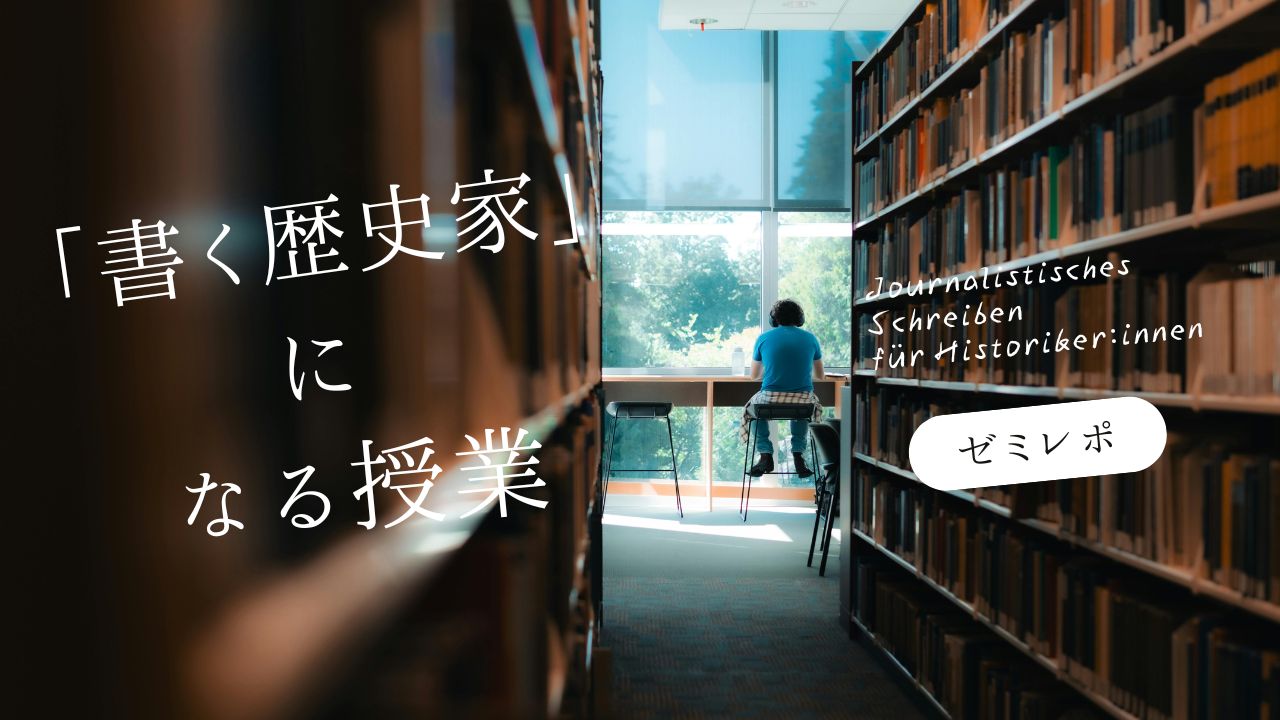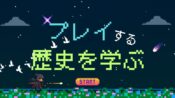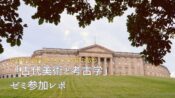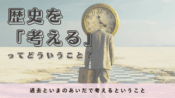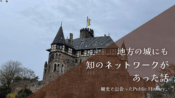「書く歴史家」になる授業|ゼミ“Journalistisches Schreiben für Historiker:innen”体験記
\ この記事を共有 /
「書く歴史家」になる授業|ゼミ“Journalistisches Sch...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣
「歴史を書くって、こんなに“調整”がいるものなのか!!!」
そう感じたのが、カッセル大学の必修ゼミ
「Journalistisches Schreiben für Historiker:innen(歴史家のためのジャーナリスティック・ライティング)」
でした。
歴史家に求められるのは、複雑なことを“正確に”伝える力。
でもこの授業では、そこにもうひとつ、“読者が理解できる形に変換する力”が問われます。
つまり、内容の飛躍を防ぎ、読者が“なぜ今この話?”と迷わないように繋ぐ“中間コンテクスト(Zwischenkontext)”で書く力。
それが、このゼミの核心でした。
【授業の様子】記事を書く、添削される、そしてまた書く
初回だけ対面で、以降はオンライン。
これは赤ちゃん連れ参加にはとても有難かったです!
私はいつも、主人の仕事が終わるまで、息子を抱っこしながらZoom越しに参加していました👶💻(授業は16-18時だったので)
メディア史の権威に“書く”を鍛えられる
メインの担当講師はRequate先生。
19〜20世紀ヨーロッパのメディア史と公共圏史の第一人者です。
著書『Journalismus als Beruf(1995)』では、「ジャーナリズムという職業はいかに社会的信頼を得てきたか」を分析し、現代の“情報を扱う倫理”を歴史的に掘り下げた研究で知られています。
近年はドイツの雑誌『ZEIT Geschichte』誌やコミュニケーション史の国際ネットワークでも活動しており、”歴史を書くこと=社会と対話すること”という視点を学生にも求めます。
この授業ではまさにその思想が実践されていて、彼のコメントはどれも「だから何?」という中間コンテクストを含めた問いに戻ってくるものでした。
一方で、もうひとつの軸を支えたのが、Matthias Band さん。
元地方紙『Westfalen-Blatt』副編集長で、2024年冬時点で「Bonifatiuswerk des deutschen Katholizismus(略称 Bonifatiuswerk)」広報として日々ニュースリリースや特集記事を手がけるベテラン記者。
Bandさんは、理論より“現場感覚”を大切にする人。
「読者が立ち止まる1行目を書け」
「記事の“いま”を掴め」
と、一文一文に赤を入れながら、“読まれる文章の礎”を教えてくれました。
各々の添削コメントに熱が入っていたのも、本当にプロ魂なんだな、と思いました!
Requate先生が文章を“どう構築するか”を問い、Bandさんがそれを“どう読ませるか”を鍛える。
理論と実践のあいだで、私たちは“伝わる歴史の書き方”を体で覚えていきました。
ドイツの歴史雑誌『ZEIT Geschichte』編集長も登壇!
ゼミの後半には、『ZEIT Geschichte』編集長(当時)Frank Werner氏 が登場し、各自のExposé(記事企画案)に丁寧なコメントをくれました。
事前に送信した各自のExposé(記事企画案)を一つずつ読み込んでくれ、それをもとに「テーマの切り口」「読者が惹きつけられる導入」「雑誌に載せるならどこを削るか」「過去の話だけど現在形で記載する」など、プロの編集視点での講評をしてくれました。
紙媒体の編集長に自分の草稿を見てもらったのは、本当に貴重な経験でした!!
【自分の問い】「伝える」と「書く」はちがう
課題では、展覧会レポート・コメント・科学コラムなど、
異なる“文体のジャンル”を通して、表現の射程を試しました。
私はもともとWebライターとして文章には慣れていたけれど、
このゼミで思い知らされたのは、「読まれる文章」と「理解される文章」は別物だということ。
とにかく添削の赤字が多かった(笑)。
でもその赤こそ、学問を社会に開く“翻訳作業”だったのだと思います。
【日本語とドイツ語の大きな違い】中間コンテクスト(文脈)
Band氏の添削では「この説明は正確だけど、誰に届くの?」と問われ、Requate先生からは「文脈の橋が抜けている(der Zwischenkontext fehlt)」と返されました。
日本語では自然に通じていた文が、ドイツ語にすると「だから何?」となるマジック。
日本語だと前後の文脈である程度理解できる文章も、ドイツ語にした瞬間により詳しく書かないといけなくなる(=中間文脈)には、本当に今も苦労させられています😅
ドイツ語で文章を書くうえで“文のあいだをどうつなぐか”という文章構造の大切さを思い知らされました。
【まとめ】「中間文脈」を意識して書く
このゼミで学んだのは、歴史を書くことは、過去を説明することではなく、いまをどう語るかを選び取る行為だということ。
事実と物語、専門と日常、そのあいだに立つ“書き手の声”を見つけること。
赤ペンだらけの原稿を重ねながら、私は少しずつ「自分の中間コンテクスト」を見つけていったのだと思います。
この“中間文脈”を意識することは、現在の課題レポート(Hausarbeit)やポートフォリオ作成だけでなく、いま取り組んでいるZINE制作にもつながっています。
研究と日常をどう橋渡しするか。
あのゼミで悩みながら見つけた問いを、今度は小さな冊子の形でも掘り下げてみようと思います。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ