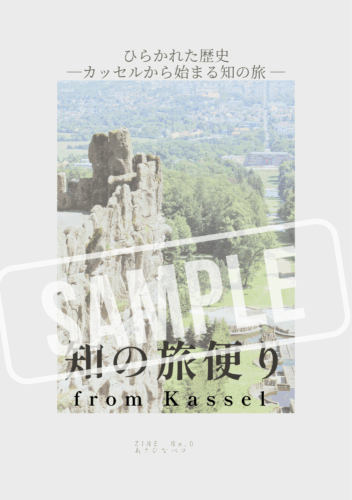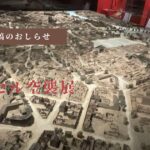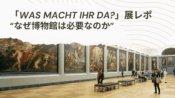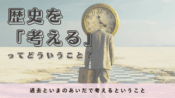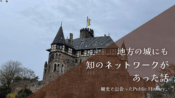カッセル大学のPublic Historyゼミに参加してみた【歴史と公共性を学ぶ体験記】
\ この記事を共有 /
カッセル大学のPublic Historyゼミに参加してみた【歴史と公共...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣
今回は、カッセル大学の修士課程「Geschichte und Öffentlichkeit(歴史と公共性) 」で開講される必修ゼミ「Einführungsmodul Master Geschichte und Öffentlichkeit(修士課程 歴史と公共 入門ゼミナール)」に参加したときの体験をまとめます。
私が現在学び研究している「歴史と公共(Publich History)ってなに?」を学ぶ入門的な内容です!
ぜひ最後まで読んでみてね!!
赤ちゃん連れで参加した冬学期のゼミ(笑)
このゼミは冬学期にしか開講されず、夏学期入学の私は受けるまで、長い“待機期間”を過ごしました(笑)。
しかも、当時は臨月→出産、尾てい骨骨折+密着大好き息子の対応で産後鬱になるというカオスな期間でもありましたw
2024年の夏学期終盤に出産したこともあり、実際にこのゼミに参加できたときは赤ちゃん連れ。
ですが、担当のカルーソ先生もなんとママ博士!!!
メールで連絡し、当日会ったときはめっちゃ笑顔で息子も併せて大歓迎!!!
さらに「泣いても大丈夫よ!」と優しく受け入れてくれたのがとても印象的でした👶✨
マジで子連れにやさしいカッセル大学。そしてFachbereich 05 Gesellschaftwissenschaftよ……(´;ω;`)子ども連れで参加を断られたことは一度もありませんでした。
【ゼミ概要】Public Historyとは何かを“体験で”学ぶ
ではさっそく、ゼミの内容を紹介しましょう!
このゼミは、カッセル大学修士課程のPublic History教育の入口にあたる授業 です。
歴史を「語る」こともまた、研究の一部である。そんなPublic Historyの精神を、理論だけでなくディスカッションや発表を通して学べます。
構成は大きく3パート。
理論編 :Public History(歴史と公共)とGeschichtskultur(歴史文化)の基礎を学ぶ専門領域編 :各時代(古代・中世・近代など)における「歴史と公共性」のアプローチを知る実践編 :Oral History(オーラル・ヒストリー)を通じた職業実践
これだけだと何言っているかわからない人大多数だと思いますので、詳しく解説します!
理論編
Public History(パブリック・ヒストリー/歴史と公共)とは、ざっくり言うと「歴史をどう社会と共有するか」を考える学問分野。
映画や博物館、記念碑、ゲームなど、大学の外で“歴史が語られる場”をどう扱うかを学びます。
授業では、専門家が書く“研究の歴史”と、市民が触れる“日常の歴史”のあいだをどうつなぐかがテーマでした。
使った教科書は、ドイツでは定番のPublic History入門書(リュッケ&ツュンドルフ)と、展示やメディアでの歴史表現を紹介する本(ガイケン&ザウアー編)などなど。
どちらも実例が多く、理論より“現場の知”に近い内容でした。
博物館もそうだけど、記念碑やモニュメントについてなんかも学んで、もうこれはワクワクが止まりませんでした!
専門領域編
カルーソ先生が基礎編を担当してくれたその後は、古代史・中世史・近現代史など、各分野の先生や講師が登場して、それぞれの時代で「社会とのつながりをどう考えるか」を紹介してくれました。
たとえば、こんな感じ↓
古代史では“神話の語り直し”
中世史では“他者イメージ(Wir und die Anderen)”
近現代史では“記憶の継承”や“メディアの中の歴史”
動物から学ぶ歴史
古代史では「神話や古代イメージが現代社会の“理想や他者像”としてどう生きているか」を考え、
そして近現代史では、難民家族の強制送還を追ったドキュメンタリー映画『Die Weggeworfenen』を題材に、メディアが作る“現代の歴史”を分析しました。
時代が変わっても、媒体が変わっても「過去をどう見せるか」というPublic History的な問いは共通しているのが面白かった!
まさに時代ごとに見る「歴史と社会」を大放出って感じ
実践編
最後のパートでは、卒業生にインタビューして「歴史を学んだ人がどんな仕事をしているのか」を探るプロジェクトに挑戦します。
ここで学ぶのが**Oral History(オーラル・ヒストリー)という手法。
これは“記録する”だけでなく、“語ること自体が歴史になる”という考え方です。
‥‥
なんだけど、ハプニング発生。
実はこの回、すごく楽しみにしていたのに申し込み制だったらしく。
それを知らず、参加できず……😂
でも、どうやら誰も受講していなかったらしく(笑)、先生に相談して、2025/26年冬学期で後輩たちに交じって別途受講できることになりました!
そのときこそ、じっくり「語りの歴史」を体験してみたいです。
こういう小さなハプニングも含めて、ドイツカッセル大学院生活は“実践の連続”です。
うまくいかなかった経験も、次の学びにつながるのがこのゼミ、いや、この修士課程の良さだと思います。
歴史とメディア:映画・展示・ゲームの中の「語り」【メディアに表れる“Public History”】
Public Historyの授業では、「どこで歴史が語られているか?」という問いを徹底的に掘り下げます。
たとえば映画、ドキュメンタリー、博物館、そして意外にもコンピューターゲーム 。
Geyken & Sauer(2019)では、こうしたメディアを“Geschichtsorte(歴史の場)”として扱い、「エンタメ的語り」と「歴史的誠実さ」をどう両立するかが論点になります。
授業では「Digital History – neue Medien, neue Inhalte? 」という回もあり、ChatGPTなどAIツールを用いた歴史表現にも話が及びました。
カルーソ先生の
「楽しさと誠実さは、決して対立しない」
という言葉が印象に残っています。
歴史を伝えるうえで“おもしろさ”を拒む必要はなく、むしろ多様な語り方を試すことこそPublic Historianの仕事なのだと感じました。
【人生初プレゼン in ドイツ】テーマ「カッセルと東京、2つの戦争の記憶」
実は私、ドイツで初めてやったひとりプレゼンがこの授業。
初めてのドイツ語プレゼンのテーマは、「Die Zerstörung von Kassel und ihre Öffentlichkeit(カッセルの破壊とその記憶の共有)」 でした!
ドイツ語ですが貼っておきます。
Kasselの記憶:破壊と再生の街
1943年10月22日、カッセルは英軍空襲により街の約85%が焼失しました。
その記憶はいま、市立博物館やカールスアウエ公園の防空壕、そしてドクメンタ(documenta) という国際芸術祭を通じて語り継がれています。
市民博物館の展示は、カッセル大学に客員教授としてきていた早稲田大学の教授も感動していたレベルでした!
1955年に始まったドクメンタは、単なるアートイベントではなく、「廃墟からの文化的再生」を象徴するPublic History的プロジェクトでした。
芸術家ヨーゼフ・ボイスの《7,000 Eichen(7000本の樫の木)》もその一例です。
芸術家のヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys)は、戦後ドイツを代表するアーティストのひとり。
「社会を変える力としてのアート」を掲げ、カッセルの国際展ドクメンタでは《7,000本の樫の木》など、芸術と市民の協働をテーマにした作品を発表しました。
彼の活動は、破壊された都市が“芸術で記憶を植え直す”という、パブリック・ヒストリー的な試みでもあり、カッセルの「再生」の象徴として紹介されることが多いです。
【東京との比較】「語る」記憶
私はこの発表で、ペコの地元にある東京大空襲・戦災資料センター (東京都江東区)との比較も行いました。
共通点は、どちらも市民が中心になって記憶を守り伝えている点。
ただし表現の方法が異なります。
Kassel:芸術や建築を通して「記憶のかたち」を再構築
Tokyo:語り部や展示を通して「記憶の声」を継承
この違いを通じて、“記憶を伝える”とは何か を深く考えられました。
この発表を経て、実際に東京大空襲資料館に行こうと思ったのですが、時間が足らず😿次回の日本一時帰国の際に行ってみようと思います!
Oral Historyと職業実践:歴史を“聴く”スキル
【学んだこと】「Public(公共)」とは“ひらかれた対話”
Public Historyの“Public”は、単に「大衆向け」という意味ではありません。
それは、「過去について共に考えるための場をひらくこと」 。
研究者が語り、市民が応答し、また新しい問いが生まれる。
その往復運動の中に、Public Historyの本質があるように思います。
英語のPublicにあたるドイツ語の Öffentlichkeit には、「公共」だけでなく「開かれた対話空間」というニュアンスがあります。
このゼミを通して私は、「歴史を“教える”のではなく、“共に考える”ことこそ大切」だと実感しました。
おわりに:歴史を開く未来へ
Public Historyは、“語る歴史学”ともいえる分野です。
部屋の外に出て、展示・映像・語りなどを通して、社会と対話すること。
それは、AIやSNSがあふれる現代にこそ必要な力だと思います。
赤ちゃんを抱っこしながら受けたこのゼミで、私は「歴史をひらく」という言葉の意味を、少しだけ実感できた気がします。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ
関連リンク