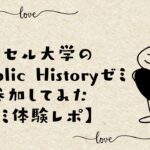【マニュフェスト】歴史を、もう一度生きるために
歴史を、もう一度生きるために
カッセル大学院に通い始めてからというもの、私にとって歴史とは、もはや過去を記述する行為ではなくなりました。
それは、他者の時間を自分の身体で生き直すことだと新しく定義づけられます。
史料を読み、言葉を探し、想像しながら、私たちは何度でも「いま」と「かつて」の境界を往復しています。
その往復のなかで、過去は「出来事」ではなく「関係」として現れる。
そんなふうに感じる瞬間があります。
つまり「語る」とは、他者とともに時間を生きることなのではないか。
そこに、学問と創作のあいだを越える何かがあるのではないか。
そんな境地に立ちつつあります。
ドイツで歴史と公共(Public History)と呼ばれる実践に出会いました。
それは、学問の外へと開かれた歴史の語りであり、市民が〈過去〉に参加するための場をつくる試みでした。
その一方で、大学の授業では「受容」という考えにもたびたび出会いました。
「受容」とは、歴史がいかに受け取られ、現代に語り継がれてきたかを問う視点です。
ですが、今日私はそれを“創る側のまなざし”から見直したいと思いました。
過去を解釈するだけでなく、もう一度物語ること。
理解したうえで、あえて無視し、想像のほうへ踏み出すこと。
その勇気の中にこそ、歴史が「現在に息づく」瞬間があるのではないでしょうか。
そして「語りの自由」は市民のものだけではなく、研究者にも、語り手にも、創り手にもあるのではないかとも感じ始めています。
過去を理解し、受け取り、そしてあえて無視して創る──
この「理解と創造の往復」に、私が思う公共の想像力は息づいているのかもしれません。
私が10月から始めた『考えるって、案外楽しい』をコンセプトにして書き続けている『知の旅便り from Kassel』と銘打ったZINEやメルマガ、そして本ブログ「あさひなペコLOG」は、その試みの延長にあり、実験ための編集室に変貌しました。
学問を離れた場所で、しかし学問の火を消さずに、語ること・描くこと・書くことを通して、思考を共有できる小さな公共空間を開くための実験です。
歴史とは、完成した物語ではありません。
いま語り直されることを待っている、未完の対話なのではないでしょうか。
歴史を書くって、たぶん「過去を調べること」「過去をただ覚えること」より、「いまをもう一度見つめ直すこと、考えること」に近い。
そんな気がして、発信し続けています。