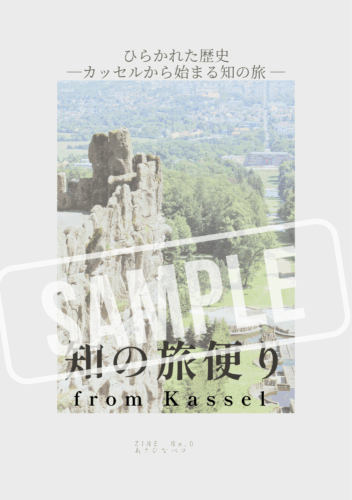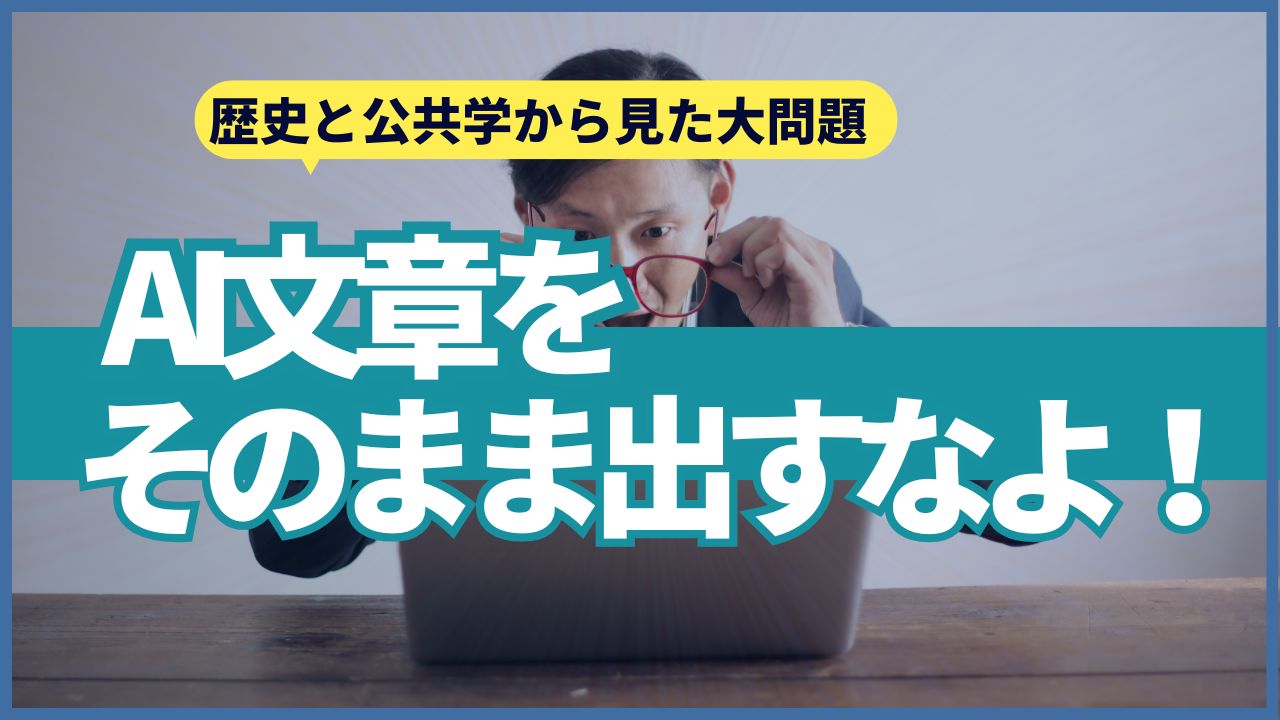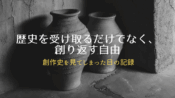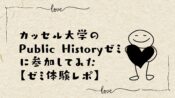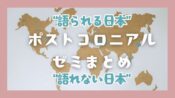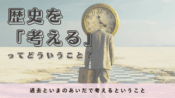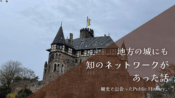【AI納品マン事件】AI文章をそのまま出すなよ!歴史と公共学から見た大問題
\ この記事を共有 /
【AI納品マン事件】AI文章をそのまま出すなよ!歴史と公共学から見た大問...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!ドイツの大学院で歴史と公共を専攻するWebライターのあさひなペコです!
わたくし先日、とある案件のチャットを見て思わず頭を抱えました。
複数人いるライターの誰かが、どうやら AI丸出しの文章を初稿としてそのまま納品 してしまったらしいのです。
その結果、ディレクターがわざわざ全員宛て(to all)で長文の注意喚起を送信していました。
ちなみにクライアントはAI使用を禁止しているわけではありません。
ただし、「AIをそのまま完成原稿にするのは絶対にやめてください」とのこと。
内容 はもっともですが、真面目に取り組んでいた他のライターまで巻き込まれてしまいました。
そりゃそうだよ、AI使っちゃダメだろという正論ツッコミがある一方で、便利なんだから使わない方が頭おかしくね?みたいに反応が分かれそうなこの感じ。
私はこのチャットを受けて正直なところ、心の中ではこう叫んでいました。
AI使うなとは言ってない。だけど、そのまま出すなよ!
便利で役立つAIの活用が、Webライター界隈だけでなく、個人事業主のライティング界隈ひいてはクリエイティブ界隈でも賑わっているようです。
でも、このようなAI納品マン事件を皆さんどう思ってる?
AIって著作権あるの?ないの?ってか著作権って誰が持つの?
自分?
オー〇ンAI?
それとも?
本記事は、カッセル大学(Universität Kassel)大学院「歴史と公共性(Public History)」専攻に在籍する 筆者によって執筆されています。 専門は古代史、とくにイコノグラフィー(図像表現)の分析を通じたパブリックヒストリーの研究。でもまだ迷っているw その一方で、ゼミ「 Geschichte schreiben mit ChatGPT 」に参加し、デジタル・ヒストリーや生成AIと歴史叙述の関わりにも関心を深めてきました。 そこで得られた学びをもとに、本記事では「AI納品マン事件(笑)」をもとに、AIと歴史の関係を学術的に検討しています。
この辺りをゼミで勉強してきたので、AIで何かを生成して世に出している方に、ぜひ読んでもらいたい。
ということで、スタート!
ソースは授業で使用したプレゼンテーション資料およびドイツ語/英語圏研究者の論文です!
歴史叙述とAI文章のギャップ ここからは愚痴を少し横に置いて、学術的に整理してみましょう。
歴史を語るとき、研究者は単に「事実を並べる」わけではありません。 重要なのは 問いを立て、解釈し、物語として再構成(ナラティブ)すること です。
一方でChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は「もっともらしい文章」を 統計的に生成 するだけ。理解しているわけではありません。 だからこそ、AIが出す歴史文章は「呼吸をしていない歴史」になりがちです。
例えるなら、教科書を丸暗記した学生が試験でそれをリピートするようなもの。正解っぽい言葉は並ぶけれど、「なぜ?」を問う力はゼロ。 このギャップこそ、「AI文章そのまま納品」が致命的にまずい理由です。
倫理的な問題点:AIを「そのまま」使うことの不誠実さ AI納品マン事件が示すのは、単なるスキル不足ではなく 倫理的な問題 でもあります。
詳しくご紹介すると、こんな感じ。
著者性のあいまい化 誰がその文章を書いたのか分からなくなる。歴史叙述において「声の主」が消えることは、信頼性を根底から揺るがします。
これって、AIが何たるかを意識していないと気が付かない問題ですよね。
信頼の崩壊 出版物やレポートが「実はAIの丸出し」だったとしたらどうでしょうか?
読者はその媒体や著者への信頼を失い、ひいては学問や教育そのものの価値が損なわれかねません。
今回のAI納品マン事件は、まさにこれ。
労働倫理の軽視 AI生成物を「自分の成果」として提出することは、真面目に時間をかけて調べ、書いた人たちを踏みにじる行為です。
今回のように、無関係なライターまで注意喚起に巻き込まれるのはその典型です。
規範の破り捨て 今回発端となったクライアント先では「AI禁止」とは言っていません。
ただ「AIをそのまま完成稿にするな」と繰り返し伝えていました。
わざわざ「AI使ってる?アンケート」まで実施していたくらいです。
つまり、ルールを無視して納品するのは、単なるスキル問題ではなく契約上の不誠実ですよね。
二重の“盗用” AIが生成する文章は、しばしば既存の著作物を学習データとしているって、知ってましたか?
私もなんだかんだ、AIにメチャクチャお世話になっていますが、「え、それどこで知ったの!?」っていうようなWW2後の哲学者の著書まで知っていました。恐ろしい。
そのうえ利用者が全くの修正なしで「自分の原稿」として提出するのは、二重の意味で他人の成果を借用しているとも言えます。
これも気づいていない人多いんじゃないかしら?
AI文章の見抜き方:チェックリスト(近日公開予定) 本記事では後日、授業資料をもとにした「AI文章チェックリスト」を掲載予定です。
→ 詳細は後日追記します。
社会的背景:AI丸投げはどこでも問題化している 「AI納品マン」の問題はライター業界だけの話ではありません。
教育現場 :学生がレポートを丸ごとAIに書かせるケースが増加。見た目は整っていても、批判的思考力は育ちません。
出版・ライター業界 :AI生成物を人間の成果と偽って納品する問題。透明性や著者性が揺らいでいます。
研究 :論文に無自覚にAI文章が混ざるリスク。出典責任が不明確になれば、学問そのものの信頼性が危うくなります。
大学で作業をしていると、会話している学生たちから「チャットGPT」の話を聞かないことがないくらいです。
本当に大丈夫かよ。
ただし一方で、 AIは歴史を広く伝える補助ツール として期待もされています。 難解な研究成果を一般読者向けに要約したり、資料を整理したりする作業では、むしろ人間の負担を減らす強力な相棒になりうるのです。
人間の役割:AIはボケ、我々はツッコミ 私自身のゼミ研究では、AIと人間の関係を日本の漫才(Manzai)の比喩で考えました。 漫才には、ナンセンスなことを言って場をかき回す ボケ と、それに冷静に突っ込む ツッコミ がいます。
AIは「もっともらしいけれどズレたこと」を言う= ボケ 。 人間は「本当にそうか?」「史実に合うか?」と問い直す= ツッコミ 。
「AI納品マン事件」の問題点はまさにここにあります。 AI(ボケ)の発言をそのまま流した結果、ツッコミ(人間)が機能しなかった。 だからこそ「AIっぽい文章」をチェックし、必要なら修正する――つまりツッコミ役を忘れないことが不可欠なのです。
この比喩はユーモラスですが、要は歴史学における**批判的検証(Quellenkritik=史料批判)**の拡張です。 「誰が語っているのか」「根拠は何か」を問い続けるのが人間の役割。AIを使う以上、この態度が欠かせません。
個人レベルのリテラシーも不可欠 制度やルールづくりはもちろん必要です。けれども、それだけでは現場は変わりません。実際に文章を書く個人が「AIっぽい」とどう見えるかを意識しないと、結局また同じ問題が繰り返されます。
私自身、ディレクターをしていた頃にライターへフィードバックを返すなかで、こんな注意をしたことがありました。 「この文言はAIっぽく見えてしまうから、少し工夫した方がいいよ」 。
当人は悪気なく書いたのですが、読み手から見れば「妙に整いすぎ」「クセがない」文章はすぐに浮いてしまいます。つまり、 AIであろうとなかろうと、“AIっぽく見える” こと自体がリスク なのです。
だからこそ、チェックリストのように「どの表現がAI的に見えやすいのか」を共有し、現場の一人ひとりが“AI臭さ”を気にできるようになることが大事なのです。
まとめ:AIは敵か、味方か AI納品マン事件をきっかけに愚痴をこぼしましたが、最後に残るのは次の教訓です。
AIを使うなとは言わない。だが「そのまま」出すのはアウト。(超重要) 歴史を語る主体は、最後まで人間であるべき。 専門性と文脈を持つ人間がAIを活かしてこそ、未来のパブリックヒストリーは豊かになる。
AIは敵ではなく、あくまで 相棒です 。
ただし、その手綱を引き、ツッコミを入れていくのは、まだまだ私たち人間だといえます。
人間のチェックと解釈力と組み合わせて使うとき、はじめてAIの本領が発揮されるのではないでしょうか。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ
参考文献
Torsten Hiltmann, Hermeneutik in Zeiten der KI . In: KI: Text. Diskurse über KI-Textgeneratoren . De Gruyter, 2024.
Raphael Besenbäck & Lorenz Prager, Künstliche-Intelligenz-Quellen. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen durch Text-KI für die Geschichtswissenschaft . De Gruyter, 2024.
Oliver Bendel, KI-basierte Textgeneratoren aus Sicht der Ethik . In: KI: Text. Diskurse über KI-Textgeneratoren . De Gruyter, 2024.
Christoph Ernst, Irina Kaldrack, Jens Schröter & Andreas Sudmann, Künstliche Intelligenzen. Einleitung in den Schwerpunkt . Zeitschrift für Medienwissenschaft , 11(21), 2019. Seminarfolien von Geschichte Schreiben mit ChatGPT? Dozentin: Frau PD Dr. Roscher, vielen herzlichen Dank!