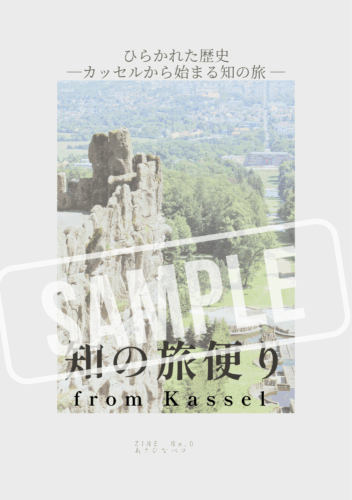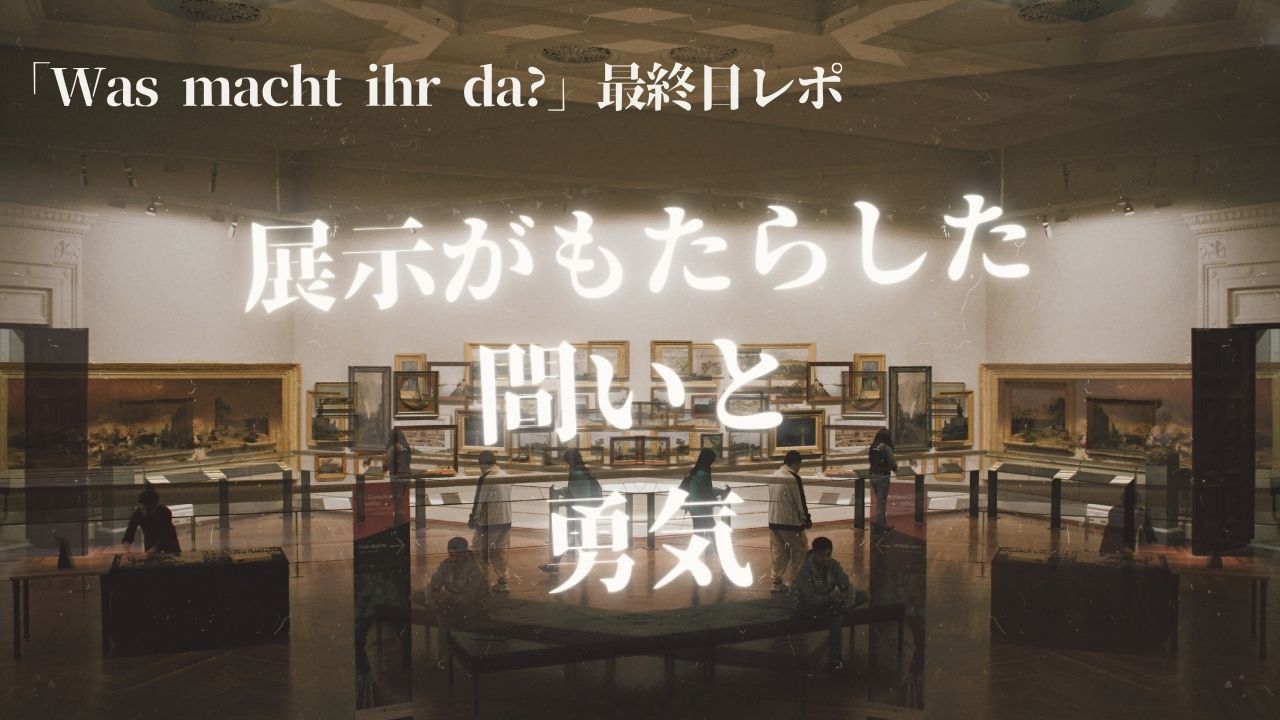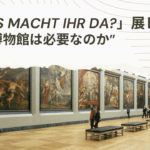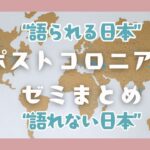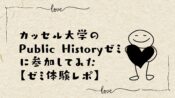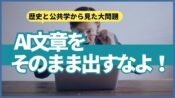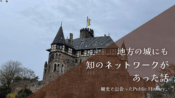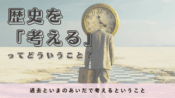『Was macht ihr da?』特別展最終日レポ|展示は何をもたらしたのか
\ この記事を共有 /
『Was macht ihr da?』特別展最終日レポ|展示は何をもたら...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっている、あさひなペコです🐣
この夏から追いかけて来た、Neue Garalie(ノイエ・ギャラリー)で開催されていた特別展
「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.(君たち、そこで何をしているの? ─ なぜ博物館が大切なのか)」
が、先日最終日を迎えました!!
実今までの人生で初めて、同じ展示会に3回以上訪問したこの展示の最終日、本当に本当に心に来るものがあったので、最速でパソコンに向かっています!!!
息子を主人に預けて、見に行って良かった!!!
の一言に尽きます。
記憶がおぼろげになる前に、ブログにしたためようと思います!!
特別展『Was macht ihr da?』のおさらい

展示の舞台「Neue Galerie」
この展示会の詳細は既にブログ記事で記載していますが、博物館の5つの機能をテーマに据えた、ありそうでなかなか見かけない、ユニークな構成です。
- Sammeln(収集)
- Bewahren(保存)
- Forschen(研究)
- Interpretieren(解釈)
- Ausstellen(展示)
「展示を展示する展示」っていう感じです(笑)
まだご覧になっていない方は、ぜひ通常のレポ記事も併せて読んでいただくと、よりこの展示のすごさが伝わってくると思います!
今回は最終日のツアーに参戦!
この日は、古代美術&考古学と壺ゼミ、プラクティクム(職業訓練)で超お世話になりまくっている、スプリッター先生による最後のガイドツアーに参加しました!
「Heute ist der letzte Tag unserer Ausstellung…(今日は展示の最終日です)」
そう挨拶を始めた先生の声には、どこか安堵と名残惜しさが入り混じっているようでした。
余談ですが、このガイドツアーでまさかの2024年夏学期にお世話になった歴史と公共の先輩と遭遇!!彼女は無事に卒業できて、今は中世の博士課程に進んだ模様です!こういうの本当にモチベーションになるし、何より不慣れなドイツの大学生活を助けてくれた人だったから、また会えて本当にうれしかった(´;ω;`)!
ガイドツアーで分かった「展示」がもたらしたもの
春の開幕からおよそ半年。
この展示が問い続けてきたのは、単なる博物館の使命ではなく、“私たち(=博物館)は、ここで何をしているのか”という根源的な自問でした。
この日のガイドツアーのテーマは、『Was macht ihr da』展の総まとめ、
「Was hat die Ausstellung gebracht?(この展示は何をもたらしたのか)」。
この問いの答えじゃないけど、何かを得たいなという期待を胸に、ツアーでは先生の言葉を必死に追いかけました。
その中でペコが特に印象に残った先生の名言をご紹介します!
展示は「問いを開く」ためにあった
先生はツアーの冒頭で、こう言いました。
„Es geht ja auch um Dialog in der Ausstellung, Partizipation und so weiter.“
「この展示は“対話”と“参加”が目的なんです。」
展示は知識を伝えるためではなく、問いを開くためにある。
誰かが何かを語り、誰かがそれを受け取る。
なんと、来館者が考え、語り合うための場として、構成されていたんです。
だからこそタイトルは「君たちは何をしているの?」と問いかける形で終わっているんです。
展示に行ったとき、まんまと友達や主人と展示について語り合っていたよ!!!
エジプトのギプス像からわかる“コピーの記憶”を展示すること
先生が次に立ち止まったのは、1885年にロンドンからカッセルへ運ばれたファラオ像の石膏複製(Gipsabguss)でした。
„Das ist kein Original, sondern eine Erinnerung an das Kopierte.“
「これは“本物”ではなく、“複製の記憶”です。」
スプリッター先生によれば、当時の博物館は、オリジナルを持たない都市が知を共有するために複製を収集していたそうです。
ですが、その背景には植民地主義的な視線も潜んでいました。
植民地については、ポストコロニアリズム理論のゼミを見ていただくと、少しピンとくるものがあるかも!
先生はその矛盾を含めて展示することが、「解釈する博物館(Interpretieren)」の役割だと語りました。
„Wir lassen die Geschichte so gehen und erzählen sie weiter.“
「この像は修復しません。ひび割れのまま、物語として展示します。」
欠けた部分も含めて「歴史」として見せる。
「完全性」ではなく「記憶の層」を伝える展示。
それが、過去を誠実に扱うということなのかもしれません。
「1秒で理解できる」世界に抗う
展示の前半で先生は、石器時代の石を展示しているブースで、スマートフォンやSNSの話を持ち出しました。
TikTokやAppleの例を挙げながら、現代の情報消費の速さを批判したんです。
その名言がコチラ👇
„Wir leben in einer Welt, die alles in einer Sekunde erfassen will.“
「私たちは、すべてを一秒で理解できると思い込んでいる世界に生きている。」
„Aber ein Buch mit 160 Seiten kann man nicht in einem Satz zusammenfassen.“
「160ページの本は、ひとつの文では要約できません。」
この言葉に、展示の核心が凝縮されていました。
博物館とは、時間を取り戻す場所なんじゃないかと。
今は情報を早く入手して、早く消費する時代です。
そんな時代の中でも博物館は、そこで「本物」を前に「ゆっくり考える」ための場所として機能しているんです。
展示室を歩く一歩ごとに立ち止まり、画面ではなく形あるものを前に、考えるための余白をもつ。
その時間こそが、この展示が訪問者にもたらした最大の経験であり、贈り物だったのです。
染色工場の木製部品──残せなかったものの物語
展示の奥には、かつての染色工場で使われていたGöpelwerk(動力伝達装置)の巨大な木製部品が置かれていました。
湿気と時間に侵食されて、ところどころ腐食しており、再現は不可能。
先生はその前でこう言いました。
„Bewahren heißt auch verlieren.“
「保存とは、失うことと隣り合わせなんです。」
„Wir haben oft mehr verloren, als wir glauben.“
「私たちは、思っているよりも多くをすでに失っている。」
それでも、失われた痕跡を展示することで、「失うとは何か」を見せることができる。
保存とは「残すこと」だけでなく、「欠けを引き受ける」ことでもあるのです。
また先生が、
「本当はここに染め布を一枚置けたらよかった」
とつぶやいていたのが印象的でした。
失われた色の記憶、その“欠け”そのものが展示の意味だったのでしょう。
写真を介して、職人さんの工房の写真や、そこで作られていた染物が見れたのですが、この工場の職人さんが作った布を、手に取って見てみたかったです。
博物館は“失われたものの不在”を語る場所でもある。
朽ちた木の歯車の前で、私は初めて「保存」という言葉の重さを実感しました。
フリッツ・トローストのトランク【勇気のかたち】
この展示の裏話が一番私の中でムネアツだったので長いよ?(笑)
ツアーの最後で、先生は1つの展示の前で立ち止まりました。
„Das ist der Koffer des jungen Soldaten Fritz Trost.“
「これが若い兵士フリッツ・トローストのトランクです。」
そこには、19歳で戦死した若者フリッツ・トローストのトランクが置かれていました。
中には、本人がコンサートをしている写真やピアノを弾く写真、音楽家を夢見て書き残した楽譜やオカリナ、指揮棒。
彼の妹が、この遺品を博物館に寄贈したとのこと。
先生、古代史の人なのに、第二次世界大戦中の展示で足を止めるのが意外!と思ったんですが、この展示のために私は4回目に行きたい!と思っていたくらい、超グッとくる展示でした。
先生は彼女のことをこう紹介したんです。
„Sie ist nach dem Krieg geboren, sie hat ihren Bruder nie gekannt.“
「彼女は戦後に生まれ、兄を直接は知らない。」
でも妹さんは、家族の中で、何十年もあったことのない兄の名前を聞き続けてきたという。
そして先生は、こう続けました。
„Wir haben sie nicht als Spenderin, sondern als Mitforscherin gesehen.“
「彼女を寄贈者としてではなく、共同研究者として迎えたんです。」
彼女は長年、手元にこのトランクを置いていた。でも、いつか「語れる場所」に置きたかった、と言っていたそうです。
今思えば、先生は妹さんの勇気に対して敬意を込めたんだと思います。
これはPublic History(公共史)の本質そのもので、“記憶を持つ者”と“それを受け取る者”の協働によって成り立つといえます。
博物館は家族を「資料提供者」ではなく、語りの継承者として扱い、展示は「彼を語る」だけでなく「彼女が語り継ぐこと」そのものを展示しているのです。
これは博物館学的にも非常に新しい姿勢だと思いましたし、単なる“展示”ではなく、記憶のコラボレーションと言ってもいいのではないでしょうか。
妹さんのインタビュー音声
ツアーの後、私は、ずっと聞きたかった妹さんのインタビューをゆっくり聴きました。
一度も見たことのない兄についてや、彼女の母親の様子、寄贈への思いを語る一言一言に、涙がこみあげた。
彼女にとってトランクを手放すことは、単に貴重な遺物を博物館に引き継ぐのではなく、家族の痛みを「公共の記憶へと開く勇気」だったのだと思います。
その勇気に触れた瞬間、私はもう、無関係な人ではいられませんでした。
展示を見ることで、妹さんの勇気に立ち会うことになるのだから。
現在への問いも
先生は最後にこう言いました。
「今日も世界のどこかで、若者が戦場にいる。
そのことを忘れないために、このトランクを展示している。」
つまり、これは“過去”の展示ではなく、現在への鏡という役割も果たしているのです。
観る人それぞれが、「私ならどう生きただろう?」と自問することで、展示は完結していきます。
展示がもたらしたものは「問い」と「時間」そして「勇気」
先生は少し笑いながら、ツアーの最後をこう締めくくりました。
„Ich hoffe, ich habe Sie bereichert.“
「少しでもあなたを豊かにできたなら嬉しいです。」
展示がもたらしたのは、知識でも答えでもなく、考える時間と、他者の記憶に触れる勇気。
ギプス像が教えてくれた「再現すること」、
Göpelwerkが示した「手放すこと」、
フリッツさんの妹が語った「受け渡すこと」。
それらすべてが、「Was macht ihr da?」という問いに対する、静かで確かな答えだったのだと思います。
展示は終わっても、問いは続いていく。
あの日のツアーで感じた“時間”と“勇気”は、これからも私の中で生き続けるのでしょう。
今日のこの展示での経験をもとに、スプリッター先生とのプラクティクムで、更に学んで来ようと思います。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ