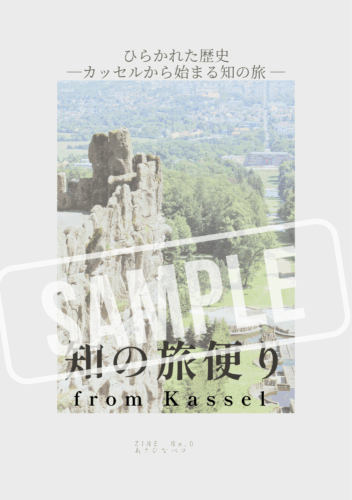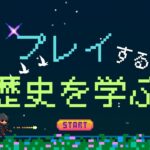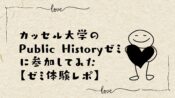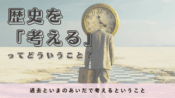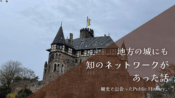【壺絵が語る記憶】カッセル大学「ギリシャの壺絵」ゼミ体験記
\ この記事を共有 /
【壺絵が語る記憶】カッセル大学「ギリシャの壺絵」ゼミ体験記
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣
壺?絵?古代?って最初は半信半疑だったのですが(笑)、気づけばこのゼミが、私の進路を決めるきっかけになったんです。
カッセル大学の古代史ゼミ「Griechische Vasenmalerei(ギリシャの壺絵)」では、ホメロスの叙事詩『イリアス』に描かれた一場面を題材に、“静けさが語る記憶”というテーマで、壺絵が伝える古代の記憶文化を学びました。
そんな私の参加記を、今回はブログにまとめてみます。
【前日譚】Splitter先生との出会いはペコが臨月の時(笑)
最初にSplitter先生に出会ったのは、2024年夏学期のゼミ「Antike Kunst und Archäologie in Kasseler Museen」でした。
臨月で受講した“古代美術ゼミ”
当時の私は臨月。
産休直前に「どうしても出たい!」と無理して受講したことを今でも覚えています(笑)
講義はカッセル市内の美術館にある古代コレクションを巡りながら行われました。
受講の参加条件としてHausarbeitを書くこと(締切り無期限)だったので、カッセル大学のSchreibberatung(ライティング相談)をフル活用させていただきました!
マジでありがとう、先生。
このゼミでは Hausarbeit(レポート) を提出し、評価は「1.7」。
正直うれしかったけど、「次こそもっといいものを書きたい!」と勝手にリベンジを誓いました😂
そして翌年度に当たる2025年、再び申し込んだのが今回の「Griechische Vasenmalerei(ギリシャの壺絵)」だったというわけです。
再会のひとことが忘れられない(笑)
再会したとき、私が「次こそはもっと頑張ります!」と意気込んだら、先生は笑ってこう言いました。
「1.7 ist schon sehr gut!(いや、1.7でも十分いいじゃないか)」
Erika Simon門下の先生、語りが熱い!
Splitter先生は、カッセル大学の古代史チームかつ名誉教授でありながら、古代美術研究の大御所 Erika Simon の門下生。
Erika Simon(エリカ・ジーモン)先生って誰? ドイツの古典考古学者(1927-2019)。 ヴュルツブルク大学名誉教授で、古代ギリシア・ローマの美術や宗教を研究。 代表作に Griechische Vasen(邦訳『ギリシア陶器』)などがあり、ギリシア祭礼研究の第一人者として知られています。 Splitter先生はその門下生にあたります。
楽天ブックス
¥6,600 (2026/02/25 06:52時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
壺絵やギリシャ美術にとにかく情熱的で、「作品の中に“物語”が生きている」とよく話していました。
授業では、展示作品の前で学生が割り当てられた壺に関してリサーチを行い、プレゼンを発表。
そしてその場で議論を繰り広げました。
そのライブ感に「やっぱドイツの大学すごいな〜!」と改めて感動しました。
【授業風景】静けさが語る“記憶”
ゼミはMuseum Schloss Wilhelmshöhe(ヴィルヘルムスヘーエ城美術館)の古代史コレクションで開催されました。
展示室のガラスケース越しに、実物の壺を前に議論するという贅沢なスタイルでした。
発表で扱った壺絵はやっぱり思い入れがあるよね
 実際のアンフォラT674の展示(ペコ撮影)
実際のアンフォラT674の展示(ペコ撮影)
特に印象に残っているのが、アッティカ黒絵式アンフォラ T674。
壺の名前、ちょっと長いですが(笑)、「アッティカ黒絵式アンフォラ」っていうのは、
ざっくり言うと古代アテネで作られた、黒い絵が描かれた液体・食料品用の壺のこと。
赤土の上に黒く焼き付けた絵で神話や日常を描く、古代ギリシャを代表する陶器のスタイルなんです。
T674描かれているのは、ホメロスの叙事詩『イリアス』の有名な一場面です。
ホメロスの叙事詩『イリアス(イーリアス)』は、古代ギリシアの英雄叙事詩で、トロイ戦争をめぐる人々の戦いや愛憎を描いた物語。 “怒れる英雄アキレウス”の物語として知られ、ギリシャ神話や西洋文学の原点とも言われています。
実は青空文庫で無料閲覧ができるそうなので、気になった人は要チェック!
青空文庫|図書カード:イーリアス
その中の一場面、「トロイの王プリアモスが、敵の英雄アキレウスに息子ヘクトールの亡骸の返還を懇願する場面」が、この壺に描かれています。
こういうのも、裏背景(=展示キャプション)を知らないと、何もわからない。だからメチャクチャ奥深いなって思いました。
アキレウスと老王プリアモス、そして足元に横たわるヘクトール。
戦いの瞬間ではなく、父が敵に赦しを請う静かな場面が描かれています。
授業中、このアッティカの壺絵についてSplitter先生が言ったひとことが印象的でした。
「Das ist keine Szene des Kampfes, sondern der Ruhe und der Bitte.」
(これは戦いではなく、“静けさと祈り”の場面です)
その瞬間、何でもない展示ケースの向こうの壺が、まるで“語り出す”ように見えました。
学んでいくうちにわかったことは、ギリシャの壺絵っていわゆるメディアと同じ役割があったみたいです。
まさか古代の器が、こんなにも“物語を語る”ものだとは思ってもみませんでした。
課題論文のテーマは、壺が語る「記憶のしかた」
今回の課題レポート(Hausarbeit)のテーマは、「壺が語る“記憶のしかた”」。
正式タイトルは、Erinnerung gestalten – Ikonographie und narrative Auswahl auf der attischen Amphora T674(記憶を形づくる——アッティカのアンフォラT674における図像と物語の選択)です。
分析よりも“気づき”を残したい
このレポートでは、作品の細部を分析するよりも、「なぜこの壺は“沈黙”を選んで描かれたのか?」という問いを軸に考えました。
ヘクトールの亡骸を前にしたアキレウスの沈黙、プリアモスの伸ばした手、背後で顔を覆う女性——その一人ひとりが、“語られない記憶”を背負っている。
そして描かれないもの、語られない瞬間。
そこにこそ、“記憶を形づくる力”がある気がしたのです。
もしここまで読んで、ギリシャの壺絵に興味を抱いた方がいれば、宜しければ以下の本をお勧めします!
私も、発表に備えて購入・活用しました!イラスト付きで古代ギリシャ美術が分かりやすく紹介されてる入門書ですよ^^
楽天ブックス
¥1,980 (2026/02/25 06:52時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
【進路の転機】“記憶の壺”が導いた道
このゼミの体験が、私の今後の道を決定づけました。
その後の授業後に、Splitter先生を引き留めて相談をしたとき、私は「古代の記憶表現をもっと深く学びたい」と話しました。
すると先生は穏やかにこう言いました。
„Ich kann Sie leider nicht betreuen – aber gehen Sie zu Herrn Ruffing.“
(私は制度上あなたの指導教員にはなれない。でも、Ruffing先生に相談しなさい。)
そのひとことが、まるで壺の中のプリアモスの手のように、私の背中を押してくれました。
そして私は勇気を出してRuffing先生のもとを訪ね、古代史専攻に進むことを決めました。
Ruffing先生との出会いの歴史は何とゲームx歴史のゼミでした(笑)
そして決まった、プラクティクム
さらに驚いたのはその後の展開。
相談の流れで、Splitter先生の勤務先である Hessen Kassel Heritage(ヘッセン=カッセル文化財機構) でプラクティクム(学外実習)を受け入れてもらえることになったのです。
このプラクティクムも卒業するために必須なのです!でも、探すのは学生が自主的に動かないといけません😂
この機関はカッセル地域の博物館・文化財を統括していて、学内のキャリアセンターでは「人気かつ倍率の高い実習先」として知られていました。
普通なら申請ルートも厳しく、受け入れまでに時間がかかるのですが、今回は先生の紹介でスムーズに決定!
まさに“壺が導いた縁”のような、不思議なタイミングでした。
【考えたこと】沈黙もまた、語りの一部
壺絵は、ただ物語を描くのではなく、「どの瞬間を、どう“語らない”か」で記憶を形づくっています。
戦いの喧騒を消し、沈黙を残す。
その選択こそ、古代の“記憶術”だったのかもしれません。
展示のキャプション、映画のワンシーン、あるいはゲームの静かな間(ま)——。
私たちが“過去を語る”ときにも、この“余白”の感覚が受け継がれているように思います。
もしかしたら、歴史を伝えるうえで本当に大事なのは、「語ること」よりも「どんな沈黙を残すか」なのかもしれません。
【おわりに】“語られない歴史”をどう伝えるか
このゼミを通して学んだのは、歴史の中には“語られない声”が確かに存在するということ。
ポストコロニアリズムのゼミで出会った『サバルタンは語ることができるか』に似てるなーと思いました。
その静けさをどう受け取り、どう伝えるか——それが、Public Historyを学ぶ私にとっての次の課題です。
このテーマをもとに制作予定のZINEでは、「沈黙の記憶」というキーワードから、展示・映像・記録の語り方をもう一度考えてみるつもりです。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ
🕊️ このゼミ体験をきっかけに、古代と現代の“語り”をテーマにした研究を進めています。
関連記事 → [修士論文テーマ決定までの道のり(準備中)]