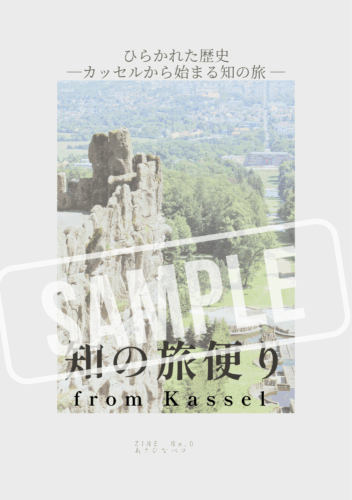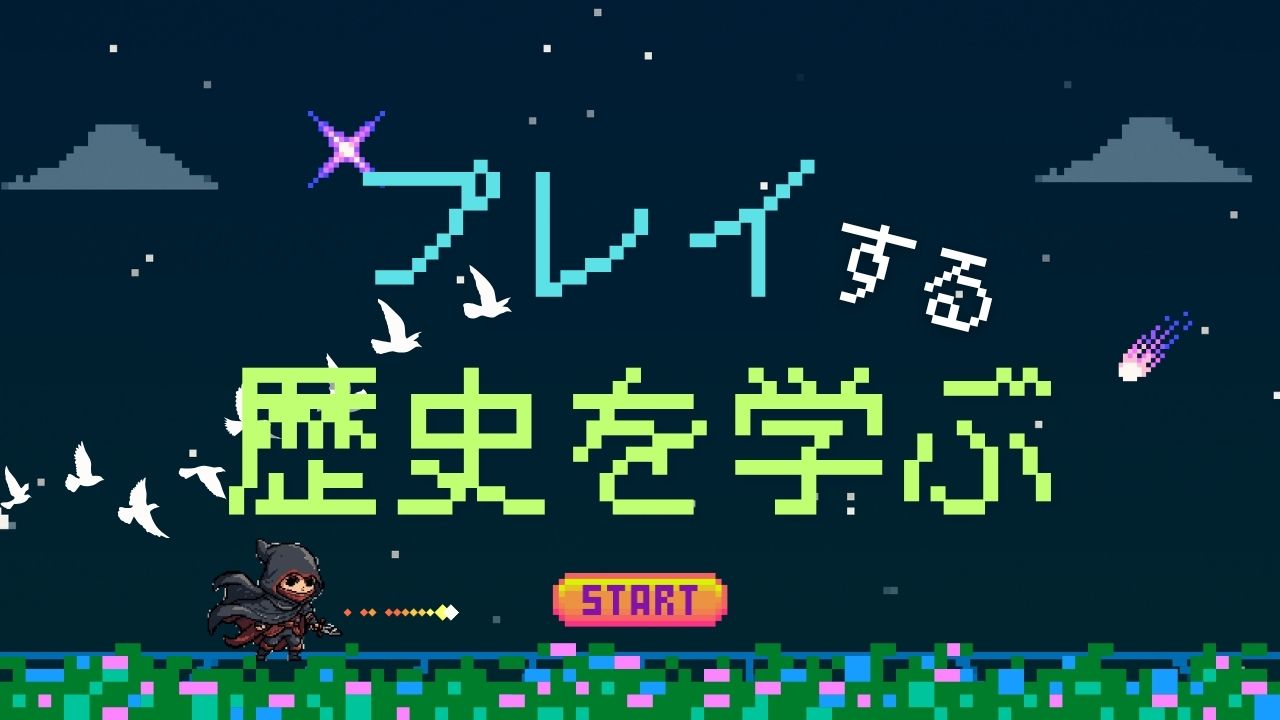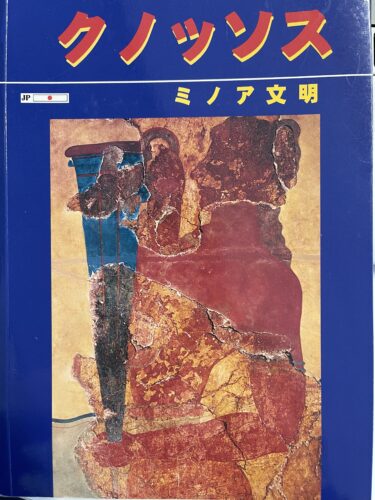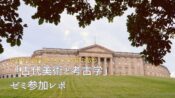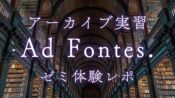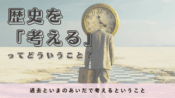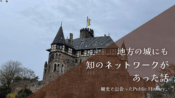【“プレイする歴史”を学ぶ】ドイツで『アサシン クリード』ゼミに参加してみた
\ この記事を共有 /
【“プレイする歴史”を学ぶ】ドイツで『アサシン クリード』ゼミに参加して...
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※
Guten Tag!
ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🎮
今回は、なんとゲームを学問にしちゃったゼミ「Assassin’s Creed Odyssey: Die Antike im Computerspiel」をご紹介します。
これまで受けて来たゼミのトップ3に入るレベルの思い入れの強いゼミなので、長いよ?(笑)
ゲームと歴史の出会い方
ゲームで歴史を体験して興味を持つというのは、オタク歴20年超の私にとってごく当たり前なことでした。
初代『戦国無双』や『三国無双』をきっかけに戦国時代に夢中になり、気づけば“歴女”として史跡を巡り、歴史上の人物を巡礼し、さらには資料を漁るオタクぶり。
だからこそ、「ゲームを通して歴史を学ぶ」 という授業が大学の正式なゼミとして存在することに、
その名も、カッセル大学の古代史ゼミ「Assassin’s Creed Odyssey: Die Antike im Computerspiel」。
ここでの学びが、のちに私の修士研究、そして博士課程へのテーマへとつながっていきます。
旅先から偶然、古代史との出会いが始まってた
偶然買った本(ペコ撮影)
じつはこのゼミを履修する少し前、夫と当時お腹にいた息子と一緒にクレタ島を旅行 していました。
強い日差しの下、クノッソス宮殿を歩きながら見た朱色の列柱、現地ガイドさんのわかりやすい案内、そして現地で手に入れた書籍。
「古代の色って、こんなに鮮やかだったのか」「この壁画にはこんな深い意味があるのか」「謎だらけとか燃える」と驚いたのを覚えています。
その体験が、まさか半年後、大学の課題で再び“デジタル上のクノッソス”として現れるとは。
初回授業の参加後、もちろんプレイステーション用のソフトを購入していました(笑)
ブックオフ 楽天市場店
¥1,331 (2026/02/25 21:51時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
【ゼミ概要】“史実”と“ゲーム”のあいだ
このゼミでは、人気ゲーム『Assassin’s Creed Odyssey』を題材に、古代ギリシアがどのように再構成され、私たちの「過去のイメージ」を形づくっているのかを分析 しました。
ゲーム好きが集まる人気ゼミ!
ゲームを題材にしたゼミなだけあって、応募時点ではすでに満員!最初は待機リストで空席待ちしてました😢
が、運よくキャンセルが出て滑り込めたんです!
“正確さ”よりも「語り方」を問う授業
Ruffing先生は、歴史表現の“正確さ”だけでなく、「なぜ、どのように過去が“語り直される”のか」 に注目するよう導いてくれました。
つまり、ゲームの中で描かれる“古代”を、単なる再現ではなく文化的な語りとして読み解く授業。
史実をなぞるよりも、「どんな物語が、どんな意図で描かれているのか」を考えることが中心でした。
【制作過程】ゼミ試験課題のビデオエッセイ「クノッソス宮殿の“もうひとつの現実”」
期末課題はビデオエッセイ。
なんで「やる!」って言っちゃったんだろうかわからないけど、ビデオエッセイ。
私は『Der Discovery-Tour-Modus von Assassin’s Creed Odyssey und der Palast von Knossos』(アサシン クリードの“ディスカバリーツアー”におけるクノッソス宮殿) を制作しました。
【ゲームの中の教室】Discovery Tourモードとは?
『Assassin’s Creed Odyssey』には、戦闘やストーリーを排して 「Discovery Tour(ディスカバリーツアー)」モード があります。
開発元のUbisoftが「教育目的でも使えるように」と設計したもので、ゲーム空間がそのまま体験型ミュージアム のように機能するのが特徴です。
プレイヤーは遺跡や都市を巡り、当時の生活・神話・建築技術などをナレーション付きで学べます。
先生のひとことでテーマが180度変わった
もともとは「ミノタウロス神話」をテーマに構想していましたが、制作前にRuffing先生に相談した際、こんなアドバイスをいただきました。
「Minotaurusは神話的すぎる。それよりも、観光地として“再構成された現実”に注目してみなさい。」
その一言で方向性が決まりました。
私は「神話」ではなく「観光としての古代」をテーマに変更。
ディスカバリーツアーモードを使って、当時のクレタ島のクノッソス宮殿やイラクリオンの再現が、現在で揃っている史実と比べてどのように構築されているかを分析することにしました。
ゲーム内のクノッソスと実際の遺跡を比較し、“リアルに見える虚構”を読み解く構成にしました。
Ruffing先生の
「MinotaurusはGodzillaみたいなもんですよ(笑)」
っていうユーモアに救われながら、私は“現実と再構成のあいだ”を探る旅に出ました。
ゲームの中で“旅をもう一度”。クレタ島との再会
ゲームのDiscovery Tourモードでクレタ島を歩いたとき、現地での旅の記憶が瞬時によみがえりました。
そして、あのとき買った図録がそのまま史実との照合資料 として役立ったのです。
Discovery Tourモードを調べる中で、偶然YouTubeの「ゲームさんぽ」シリーズに出ていた古代ギリシア研究家の藤村シシンさんを知りました。
学術的知識をわかりやすく語るその姿に、「ゲームと歴史の対話って、こういう形でできるんだ!」 と衝撃を受けたのを覚えています。
VIDEO
シシンさんのコメント、すごく参考になりました!!
内容的にも面白いので、興味ある方はぜひぜひ!!
現実の旅行とデジタル空間の再訪が重なり合う、不思議な制作体験でした。
動画編集スキル皆無のペコ、良くやり遂げたと思います。
自分偉い。
この人生初の動画編集課題が思わぬフィードバック結果だったんです。
【フィードバック】メールのやり取りから始まった研究のターニングポイント
作品を提出した後、Ruffing先生からメールで
「hervorragendes Videoessay!!!(素晴らしいビデオエッセイです!)」
とコメントをいただきました。
まさか15点満点をもらえるとは思わず、思わずバス停で人目をはばからず「よっしゃー!」と言ってしまったのを覚えています(笑)。
先生の問いかけが生んだ“気づき”
その後、何度かメールのやり取りをする中で、先生から
「日本の歴史文化や古代史にも興味はありますか?」
という質問をいただきました。
当時の私はまだ別の研究テーマを考えていたのですが、ちょうどその頃、別の授業で“ギリシアの壺絵”を題材に発表したことがきっかけで、「絵や映像を通して過去を語る」というテーマに改めて強く惹かれていきました。
またこの先生が以前産休で中途半端になってしまったゼミの担当者(古代史の名誉教授)なんですよね。
この人に思わず、授業後に何度か雑談レベルで相談したほど迷ってました(笑)
勇気を出して送ったメール、そして思いがけず示された“博士への道”
そこから勇気を出して、もう一度先生に連絡。
面談では、これまでのビデオエッセイの話から、私が日本の文化やポップカルチャーの中に見える古代への関心を語りました。
するとRuffing先生のほうから、思いがけない提案がありました。
「Griechenland und Rom in der japanischen Populärkultur —
その瞬間、心の中で小さく
と声を上げたのを覚えています。
自分の「好き」が、研究のテーマになる。
その可能性を先生のほうから示してもらえたことで、
私は初めてこの道を“自分の研究のルート”として意識しました。
ということで、古代史x歴史と公共で修士論文を書くことに決めました👏
【考えたこと】フィクションはどこまで“歴史”になりうる?
デジタルの中の歴史は、正確さよりも“体験のリアリティ” を重視します。
それは危うさでもあり、同時にPublic Historyの核心でもあります。
Public History の研究者 Martin Lücke と Irmgard Zündorf (2018) は、Public Historians が「史実への信頼性を確保しつつ、感情や美的魅力という観衆の正当な期待にも応える必要がある」という二重の課題を担うと述べています。
*Lücke & Zündorf 2018, Einleitung S. 11(原文では「Public Historians müssen zugleich für die Evidenz der Geschichte verantwortlich sein – und den Wunsch nach Emotion und Ästhetik befriedigen」と表現されている。)
このバランスこそ、『Assassin’s Creed Odyssey』のような
『Assassin’s Creed』シリーズが描く世界はまさにその実験場。
史実と物語、知識と感情のあいだで、歴史がいかに語り直されるか を体験できるのです。
国内向けで言うなら、戦国無双や三国無双なども当てはまるよね!
【まとめ】古代は今も、私たちのエンタメの中に
『Assassin’s Creed Odyssey』のゼミで感じたのは、古代は決して遠い過去ではない ということでした。
『アサシン クリード』の古代ギリシャ、『テルマエ・ロマエ』のローマ、『ドリフターズ』のスキピオとハンニバル、『Fate』シリーズや『HADES』シリーズに現れる神話の断片。
私たちは、映画やマンガ、ゲームを通じて知らず知らずのうちに古代と出会い続けています。
その物語の中に息づくのは、かつての世界そのものではなく、「今の私たちが見たい古代」 なのかもしれません。
アサクリのゼミは、そんな“生きている古代”を学問の目で見つめ直すきっかけをくれました。
これからも、歴史がどんな形で語られ、感じられていくのかを追いかけていきたいと思います。
最後まで読んでくれてありがとダンケ!
あさひなペコ
🕊️ このゼミ体験をきっかけに、古代と現代の“語り”をテーマにした研究を進めています。
関連記事 → [修士論文テーマ決定までの道のり(準備中)]